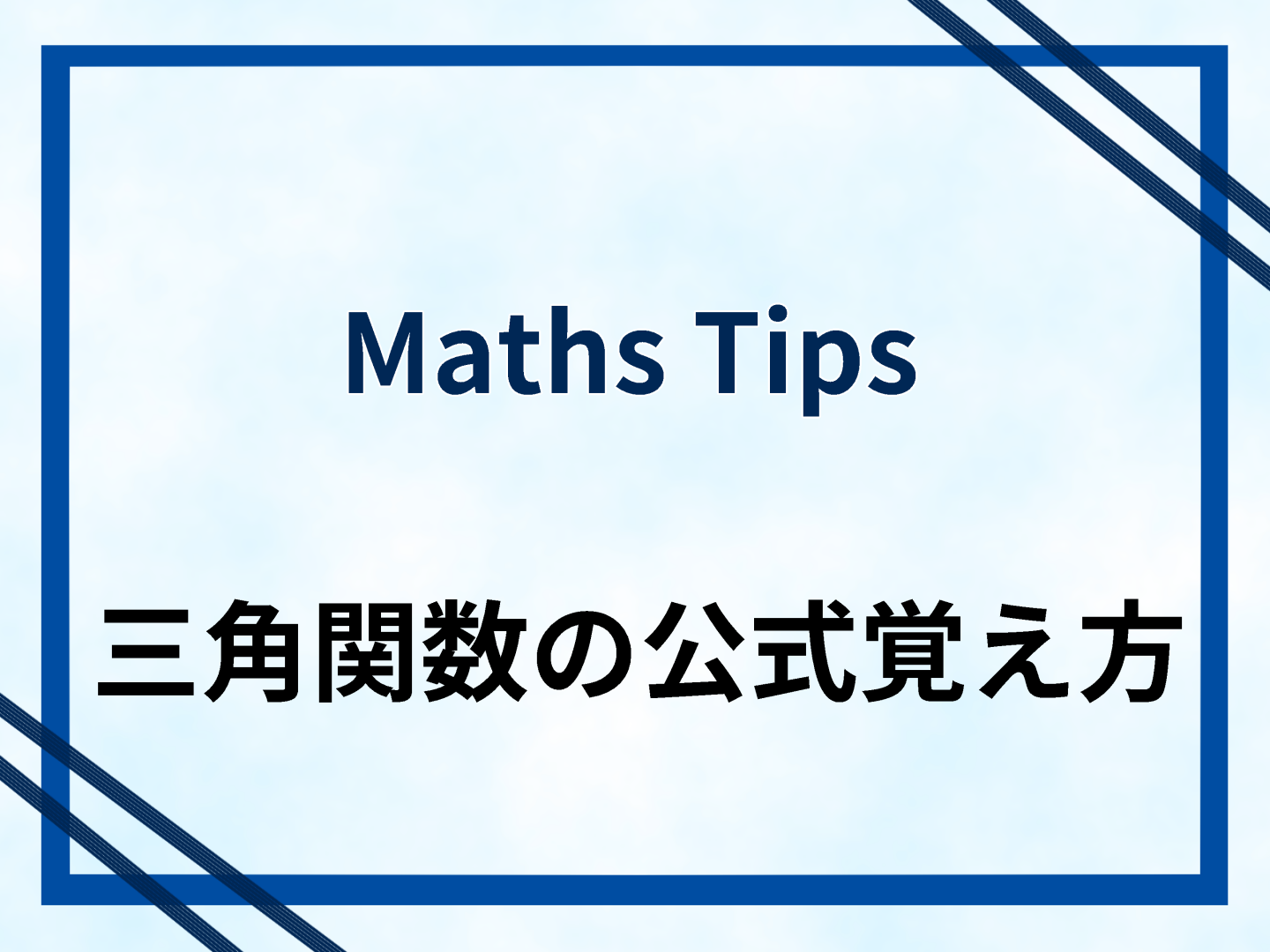三角関数の公式は多岐にわたり、覚えるのが大変と感じる方も多いでしょう。社会の年号を覚えるときの語呂合わせのように、覚えてしまいたいかもしれません。数学において、このような丸暗記は無意味、とは思いませんが、丸暗記だけでは得られるメリットが少ないと思います。
三角関数の公式を証明しておくことで、この分野における重要な式変形や考え方を知ることができます。また公式の導出方法を知っていれば、そもそも多岐にわたる三角関数の公式のほとんどは暗記する必要すらありません。
本記事では、単なる丸暗記では得られない、公式を証明することの重要性を紹介します。
1 定義、概念の理解が深まる
三角関数に限らず、公式 (formula) や定理 (theorem) の証明では、定義 (definition) から考えることが良くあります。通常の問題演習ばかりでは、定義を使うことは必ずしも多くないので、いつの間にか定義を忘れてしまいます。
定義を理解していれば当たり前の性質であっても、理解が不十分であれば、それら性質に気づかず、数学の理解が進まないこともあり得ます。例えば、三角関数の定義は単位円で与えらるほか、適当な正の実数 r に対して、半径 r の円で与えられることもあります。同じ概念にもかかわらず、半径が変わってもよいのでしょうか?
実は三角関数は半径の値に依存しません。三角関数を定義する円の半径が 1 だろうと、 2 だろうと、同じ角度に対しては常に同じ三角関数の値が返されます。実際、半径 1 の円と、それを r 倍した半径 r の円に対して、三角関数の値を計算すると、同じ角度では同じ値になります (Figure 1)。 r は任意の正の実数をとりますから、任意の半径に対して三角関数の値は変わらないという結論になります。
したがって、三角関数を定義するにあたって半径 1 の円でも半径 r の円でも構わない、ということになります。

[三角関数は半径に依存しない]
“定義は一度だけ習ったけれど、普段使わないので忘れてしまった”というのはよくあることです。しかし、定理の証明を行い、定義の理解を深めることで、上記のような三角関数の性質についてよく知ることができます。
2 重要な式変形や考え方
三角関数の公式を証明することで、重要な式変形を知ることができます。例えば以下の2倍角の公式を見てみましょう。
2倍角の公式
\sin{2\theta} = 2\sin\theta \cos\theta \tag{1}
この公式は加法定理を使って簡単に証明することができます。
まずは加法定理から始めます:
\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B
ここで A = \theta, B = \theta のとき、以下が成立します:
\begin{aligned} \sin(\theta + \theta) &= \sin \theta \cos \theta + \cos \theta \sin \theta\\ &= 2 \sin \theta \cos \theta. \end{aligned}
これで証明できました。加法定理は A + B という角度を A だけ、 B だけのように分解することができます。特に A, B が同じ値をとる条件においては2倍角の公式を表します。
では、以下の式はどのように変形できるでしょうか?
\sin(3 \theta)
いわゆる3倍角の公式に現れる式ですが、これも2倍角の公式と同様にして変形することができます。先ほどの2倍角の公式の証明で説明した通り、加法定理は A + B という角度を A と B に分解することができます。 3 \theta = \theta + 2 \theta ですから、加法定理を使えば、 \theta と 2 \theta に分解できそうです:
\begin{aligned} \sin(3 \theta) &= \sin (\theta + 2 \theta)\\ &= \sin \theta \cos 2 \theta + \cos \theta \sin 2 \theta. \end{aligned}
ここで \cos 2 \theta や \sin 2 \theta が現れますから、2倍角の公式を適用しましょう:
\begin{aligned} \sin \theta \cos 2 \theta + \cos \theta \sin 2 \theta &= \sin \theta (1 - 2\sin^2\theta) + \cos \theta (2 \sin \theta \cos \theta) \qquad (\because \text{2倍角の公式})\\ &= \sin \theta - 2 \sin^3 \theta + 2 \sin \theta \cos^2 \theta\\ &= \sin \theta - 2 \sin^3 \theta + 2 \sin \theta (1 - \sin^2 \theta) (\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1)\\ &= 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta. \end{aligned}
したがって、 \sin(3 \theta) は以下のように変形できます:
\sin(3 \theta) = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta.
公式を覚えることにも意味はありますが、それよりも重要なことは、“なぜ加法定理を使ったのか”、という証明のアイディアを理解しておくことです。今回は加法定理が A + B という角度を、 A と B に分解することができる、という性質を利用しました。
三角関数の公式の証明を通して、代表的な式変形や、証明のアイディアを知ることができ、応用力の育成につながります。
3 直感的理解
\sin \theta や \cos \theta は -1 から 1 までの値しかとりません。つまり、以下の式が成立します:
\begin{aligned} -1 &\le \sin \theta \le 1,\\ -1 &\le \cos \theta \le 1.\\ \end{aligned} \tag{2}
三角関数はなぜこのような値をとるのでしょうか? Section 1 でお話ししたように、三角関数の公式の証明を通して、定義自体の理解が深まります。そして定義の理解が深まると、Equation 2 のような性質を直感的に理解できます。その結果、“うっかり条件を忘れてしまった”など、些細なミスを減らしたり、結果の不自然さに気づくことができます。
Equation 2 であれば、三角関数の定義 \sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r} を使います。この定義を理解していれば、y や x は円周上の点の座標ですから、 -r から r までの値しかとりません。したがって Equation 2 が成立することがすぐにわかります。
三角関数の定義に慣れていれば、上記のような思考は自然と行えます。結果として \sin \theta の値が (例えば) 2 になった時には、すぐに不自然さに気づくことができます。もちろん Equation 2 を丸暗記していても、三角関数の値がおかしいことに気づくことができると思います。しかし、三角関数の性質は Equation 2 の他にも多くあります。そのすべてを理解せずに丸暗記していては、“うっかり条件を忘れてしまう”ことが、多くなると思います。
4 覚える必要のある公式の数が減る
三角関数の公式はかなり多いですが、公式の証明方法を理解しておけば、覚えておく必要のある公式の数は、かなり少なくなります。私は三角関数の公式を、2つのグループに整理しています。
- 三角関数の定義を使って証明されるグループ
- 加法定理を使って証明されるグループ
つまり、定義と加法定理さえ覚えておけば、他の公式は必ずしも覚える必要はありません。定義はそもそも理解して覚えておくものですし、加法定理は証明が少し面倒なので、試験に向けて覚えておく必要があります。ですが、公式の証明に慣れておけば、覚えるべき証明の数は大きく減ります。三角関数の場合は、公式の証明にあまり手間がかからないので、試験中にさらっと公式を導出することができ、実用性があります。この点も、丸暗記ではなく公式の理解によるメリットだといえます。
5 証明に慣れるためには
公式の証明は一度行っただけで自然と身につくものではありません。繰り返し導出を行ってみてください。重要なことは公式の導出過程で、「なぜそのように考えたかを自分なりに整理しておくこと」です。「次回自分で導出できるためには、何を知っておけばよいか」このことを常に考えながら取り組んでみてください。公式の丸暗記と違い、考え方というのは理解してしまえば案外忘れづらいものです。
合わせて公式を使った問題を繰り返し解いてください。問題を解く際には公式を見ながらでも構いません。繰り返し公式を使うことで自然と公式が身についてきます。またその都度公式の導出を行ってもよいでしょう。公式を忘れていてもすぐに導出できます。
6 まとめ
公式の証明は遠回りなようですが、本気で数学の力を高めたいのなら、避けては通れない道です。そして単なる丸暗記と比べ、三角関数における基本的な考え方や代表的な式の変形方法など、応用へつながるさまざまな重要なことを学べます。丸暗記ではなく、公式の導出と問題演習を繰り返し、自然と公式を証明できるようになりましょう。